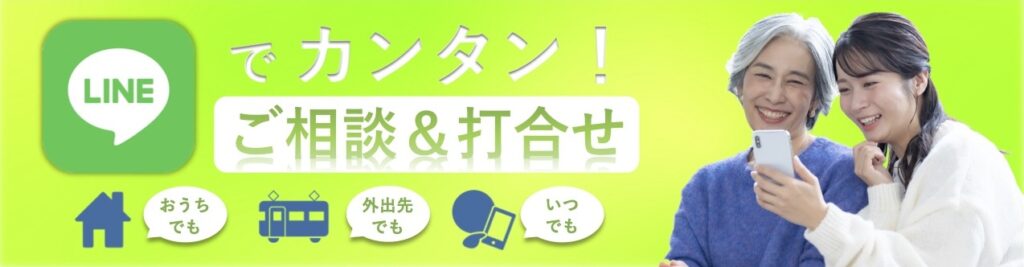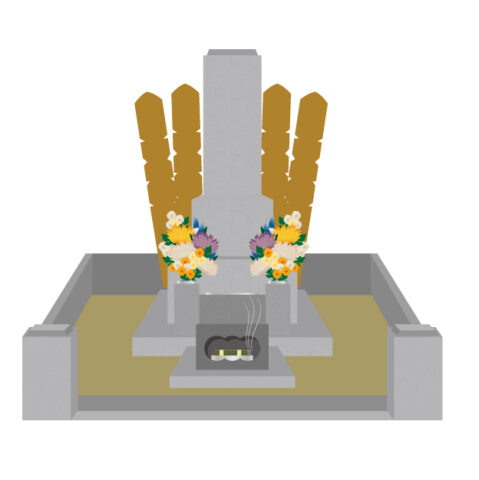お位牌ガイド いつまでに作るもの?選び方から開眼供養、役割や種類まで紹介
野田市 で 樹木葬 ・ 永代供養墓 のご相談は、平成東武霊園へ。
ご相談・ご案内会開催中。ご予約はこちらから。
日本の多くの家庭のお仏壇にある「位牌」。
位牌は、多くの家族にとって故人との絆を象徴する重要な存在で、故人を偲ぶために大切にされているものの一つとされています。
納骨に関わることに関しては、いざその時になってみないと分からない事がたくさんあります。
位牌についても、いつまでに作るものなのか、どんなものを選んだらよいかなど、情報が少ないため疑問を持っている方が多いと思います。
今回は、そんな位牌について解説していきます。
目次
位牌ってなに?
位牌は、亡くなった人の戒名や俗名、命日などが記された木製の板です。
多くの家庭では、仏壇の中心に置かれることが多く、故人の魂が宿ると考えられています。
位牌には、葬儀の時から四十九日にまで祀る「白木位牌」と、四十九日法要後から、白木位牌に替えて仏壇に祀る「本位牌」というものがあります。
◇白木位牌
白木位牌は、故人が亡くなった直後から、本位牌が完成するまでの間に使われる一時的な仮のお位牌です。
「仮位牌」と呼ばれることもあります。
白い木で作られることが多いため、このように呼ばれています。
本位牌が完成するまでの間は、白木位牌が仏壇に置かれ、供養の中心となります。
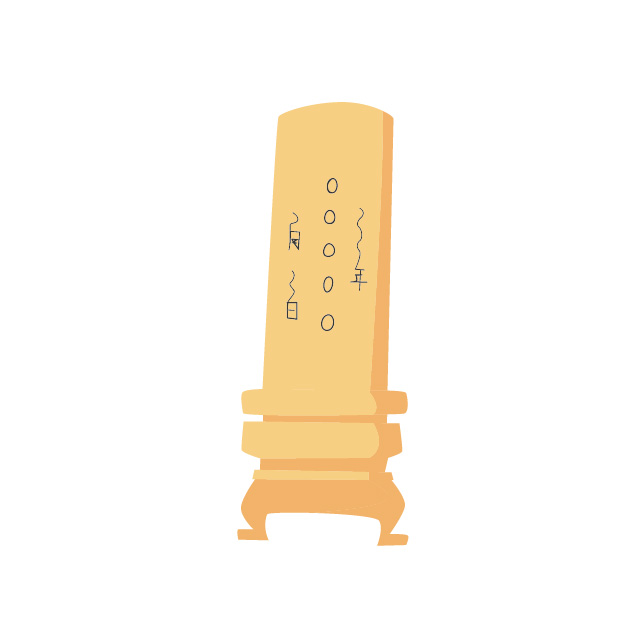
◇本位牌
本位牌とは、故人のために作られる最終的で正式な位牌のことです。
故人が亡くなった後、一定期間使われる白木位牌に代わるもので、家族が長期にわたって故人を供養するための重要な役割を担います。
法要の日に、僧侶が白木位牌から魂を抜いて、本位牌に魂を入れ替えてくださる(開眼供養)ので、その本位牌を仏壇に置くことになります。
本位牌は、木材、漆塗り、金箔が施されていたり、様々な種類のものがあります。
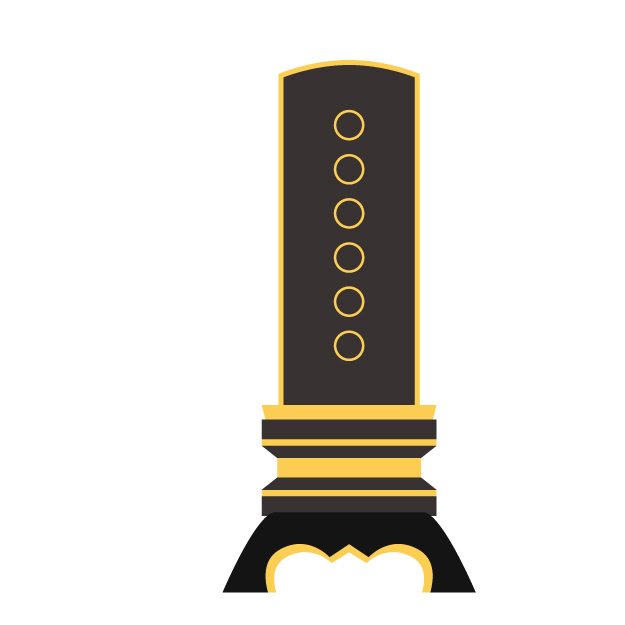
◇位牌の役割
位牌は、故人の魂を象徴する大切な供養の道具です。
- 故人の象徴としての存在
- 遺族が日々の供養を行う対象
- 命日や法要の際にお祀りするもの
特に、仏教では位牌が故人の霊の依り代(よりしろ)とされています。
仏壇は故人が帰る場所で、位牌は故人の魂が宿る場所とされています。
毎日お参りすることで、故人をいつまでも忘れずに供養し、感謝の気持ちを伝える役割を果たします。
位牌はいつまでに用意するもの?
故人の四十九日法要までに、本位牌を準備するのが一般的です。
これは、亡くなってから四十九日後、故人の魂が浄土に往生すると言われている仏教の考えからきており、四十九日法要の際に僧侶に「開眼供養」をしてもらいます。
白木位牌は、一般的には葬儀のタイミングで葬儀会社から購入できることが多いです。
ですが本位牌は、仏具店などに注文して遺族が用意しておかなくてはいけません。
位牌には故人の戒名や年齢などの文字を入れなくてはいけないので、本位牌の完成までには数週間の時間がかかります。
四十九日法要の日程を考え、早めに購入しておく必要があります。
ただし、それぞれの地域や宗派によって位牌にも多少の違いがあります。
一般的には、浄土真宗は、故人の魂はすぐに成仏すると考えられているため、位牌を用意しないと言われています。
浄土真宗では位牌の代わりに、「法名軸」と呼ばれる故人の名前が入った掛け軸や、「過去帳」と呼ばれる故人の名前や死亡年月日が記載された帳簿を使用したりします。
ですが、家庭によっては、日常生活で故人を供養するために、手を合わせる対象として位牌を用意している場合もあるので、事前に家族と確認しておきましょう。
位牌の開眼供養(魂入れ)とは?
位牌の開眼供養とは、「魂入れ」とも呼ばれ、四十九日法要とともに僧侶に依頼して行ってもらう儀式です。
白木位牌から故人の魂を抜いて、本位牌に魂を移します。
「開眼」とは、仏像を作るときに「最後に目を描き込むことで仏像の目を開き魂が入る」と言われていることから、開眼供養という儀式が慣習化するようになりました。
開眼供養を行うことで、本位牌が故人の魂が宿ったものへと変わるため、とても重要な儀式とされています。
開眼供養を終えた後は、白木位牌はお寺に納めて「お焚き上げ」などを行ってもらいます。
魂の宿った本位牌は、仏壇の中心に置かれることが一般的で、日常の祈りや法要の際に重要な役割を果たします。

位牌の選び方~大きさや種類はどんなものを選ぶべき?~
インターネットや仏具店で、いろいろなタイプの位牌を見かけると思います。
基本的には、位牌には特に決まりはないので、仏壇の大きさやデザインに合わせて作ったり、故人のイメージできるものを選んで問題ありません。
ただし、いくつかの注意点もあります。
◇位牌の選び方
①ご先祖様の位牌より小さいサイズ
ご先祖様の位牌より大きくならないよう、同じか少し小さいサイズにするのが一般的です。
これは、ご先祖様への敬意を表し、既にある位牌より大きくしないという習わしから来ています。
➁仏壇の大きさに見合ったサイズ
初めて位牌を作られる場合は、仏壇の御本尊よりも小さいことが基本になります。
位牌が大きすぎて御本尊が隠れないように注意しましょう。
仏壇の大きさに合わせて、バランスの良い位牌を選ぶとよいでしょう。
◇位牌の種類
位牌には、故人一人ひとり独立した「板位牌」というものと、位牌が10枚くらい一緒に入る「繰出位牌(回出位牌)」というものがあります。
| 位牌の種類 | 特徴 | 用途 | 管理方法 |
|---|---|---|---|
| 板位牌 | 故人一名分の戒名や俗名が刻まれた一般的な位牌。基本的には1名分だが、夫婦位牌も存在する。 | 個人または夫婦の供養 | 仏壇に安置し、日々供養する。 |
| 繰出位牌(回出位牌) | 1つの位牌に戒名が書かれた札板を10枚納めることが可能。ご先祖様の位牌をまとめる際に用いる。 | 複数の故人を一つの位牌にまとめる | 札板を命日の順番で並べ、命日が過ぎると後ろへ回して管理する。 |
板位牌
一つのお位牌に対し、故人一名分の戒名や俗名が刻まれた位牌です。
お位牌と聞いて思い浮かべる一般的な位牌です。
基本的には一つに1名が基本ですが、故人となった夫婦を祀る際には、ご夫婦連名の「夫婦位牌」というものが用いられることもあります。
繰出位牌(回出位牌)
繰り出し位牌は、1つの位牌に戒名が書かれた札板を10枚納められるものになります。
基本的には、ご先祖様の位牌が増えた時に位牌をまとめるために用いられます。
札板を命日の順番で重ねて入れておき、それぞれの命日が終わると、後ろへ回して、常に次の命日を迎える札が前に来るようにします。
初めて位牌を選ぶ場合は、基本的には板位牌となります。
位牌が仏壇に入りきらなくなった場合の対処方法
位牌がご自宅にたくさんある場合は、仏壇に入りきらなくなってくることもあります。
その場合の対処方法を紹介します。
◇先祖代々の位牌、夫婦位牌にまとめる
「〇〇家先祖代々之霊位」というかたちで、ご先祖様の位牌を板位牌に一つにまとめることが出来ます。
また、繰り出し位牌を作ることも方法の一つです。
繰り出し位牌には戒名を記録しておくための板が10枚程度入るので、ご先祖様のお位牌を一つにまとめて収めることが出来ます。
また夫婦位牌と呼ばれる一つの位牌に夫婦連名で位牌を作ることも可能です。

◇古くなった位牌を処分する
位牌は故人の魂が宿っており、長く大切に扱われるものなので、処分はしないことが基本です。
しかし、位牌を新しく用意したり、作り替えたりしたときなどは、古い位牌を処分する必要があります。
また、新居への引っ越しや年忌法要が終了した時期に本位牌を処分する「弔い上げ」を行う家庭もあります。
そのような場合で位牌を処分するときは、位牌を作ったときに魂を入れる「開眼供養」を行うのと同様に、魂を抜いてもらう「閉眼供養」を執り行わなくてはいけません。
閉眼供養をすることで、故人の魂の宿った位牌を、単なる「モノ」にしてもらうことができ、故人やご先祖様の霊を天に還すことが出来ると考えられています。
閉眼供養された位牌は、お焚き上げしてもらうことができます。
また、自宅で仏壇や位牌の維持・管理が難しい方の場合は、閉眼供養をせずに寺院に預けることで、家族に代わって永代供養してもらえる場合もあります。
位牌は必ず作らなくてはいけないもの?
位牌は故人を供養するための大切なものですが、必ず作らなければならないという決まりはありません。
仏教の宗派によって位牌の扱いが異なるため、必要かどうかは宗派によって異なります。
浄土真宗
原則として、位牌を作らない宗派と言われています。
浄土真宗では、亡くなったらすぐに阿弥陀仏の元で極楽浄土へ往生すると考えられているため、「魂が宿る依り代としての位牌」が不要と言われています。
位牌の代わりに法名軸や過去帳を作って供養をしていきます。
ただし、地域の習慣や家族の意向で、位牌を作ることもあります。
位牌を作るかどうかは、宗旨・宗派にこだわらず、家族と相談して決めて行きましょう。
おわりに
位牌は、故人を偲び、その魂を尊重する日本の伝統的な文化の一つです。
故人が亡くなった後も、家族の生活の中にその存在を継続させ、供養するための大切な役割を担っています。
位牌は故人の魂が宿る場所とされています。
社会の在り方の変化に伴い、供養の方法も変化してきていますが、故人をいつまでも供養していきたいという気持ちから位牌が必要と考える方は多いです。
ただ、位牌を作るかどうかは、宗派や地域、それぞれの家庭によって異なります。
事前に家族と相談や確認して、選んでいくことが大切です。
千葉県野田市にある平成東武霊園には、一般墓から永代供養墓まで、多彩な区画の様々なタイプのお墓がございます。
それぞれの家族の価値観や供養の形から選択していただくことが出来ます。
大切な方々と共に、ご先祖様と、これから繋いでいく家族のために最善のお墓・供養の形を選択していただけばと思います。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
お問い合わせはこちら
- 関連霊園 -