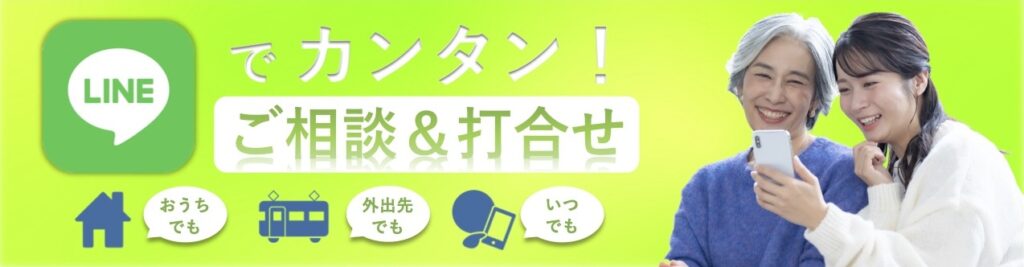お墓への彫刻 いつまでに、どこに依頼する?戒名がない場合などについても解説
野田市 で 樹木葬 ・ 永代供養墓 のご相談は、平成東武霊園へ。
ご相談・ご案内会開催中。ご予約はこちらから。
お墓参りに行くと、墓石の側面や、墓誌に、ご先祖様の戒名や名前などが彫刻されている墓所をよく目にするかと思います。
お墓への戒名や名前の彫刻は、故人を供養し、その記憶を永く残すために行われます。
しかし、いざ亡くなった時に、彫刻を必ずするべきなのか、彫刻をするときはどこに頼めばいいのか、などといった疑問を持つ人が多いのではないでしょうか。
今回は、初めて彫刻を検討する方でも安心して進められるよう、戒名彫刻の基本的な意味や流れ、相場、業者選びのポイントなどを分かりやすく解説します。

目次
戒名とは
そもそも、戒名とはなんでしょうか。
戒名は、仏教の教えに基づいて故人に与えられる名前です。
一般的には亡くなったあとに授けられます。
生前の行いや人柄を反映し、故人が仏の弟子となった証とされています。
基本的には僧侶に依頼してつけてもらいます。
戒名を付けるのには、様々な理由があります。
故人の浄化と供養
戒名を与えることで、故人の過去の罪や煩悩を清算するという意味合いがあります。
戒名には、故人が浄土や極楽へと生まれ変わるための祈りや願いが込められています。
次の世界への名前として
戒名は死後の世界での新しい名前として与えられます。
これにより、死者は次の世界での生を迎える準備が整うとされています。
家族や親族とのつながりの証
一族や家族の間で同じ戒名の一部を受け継ぐことがあります。
これにより、一族や家族の絆やつながりを象徴する役割も果たしています。
個人の特徴や願いを反映
戒名は、故人の生前の行動、性格、遺族の希望などに基づいて選ばれることが多いです。
そのため、戒名には故人の特徴や家族の願いが反映されます。
戒名についてもっと詳しく
なぜお墓に彫刻をするのか
お墓に必ず戒名や名前を彫刻しなくてはいけないというルールはありません。
では、なぜ多くのお墓で彫刻をされているのでしょうか。
故人を永遠に記憶するため
墓所に戒名や名前を刻むのは、故人を永遠に記憶するためのものです。
石に彫刻された名前は、時間の経過や自然の力に耐えて残るため、後世にもその人の存在を伝えることができます。
故人の魂への敬意や尊重を示す象徴
また、戒名や名前を石に彫刻することは、故人への敬意や尊重を示す象徴ともなっています。
◇戒名を持っていない場合の彫刻
戒名を持っていない場合でも、お墓への彫刻を行うことは可能です。
その場合、故人の俗名(生前に使用していた名前)を彫刻します。
以前は、仏教葬儀の場合は、戒名を付けることが常識でした。
そのため古くからある墓所には、主に戒名が彫られていることが多いかもしれません。
しかし、最近では宗教的な背景や価値観の多様化により、戒名を付けないという家族も増えてきました。
その場合、お通夜や告別式も俗名で行い、墓石への彫刻も俗名でするというかたちになります。
これは日本の社会が、宗教や伝統に縛られず、故人や家族の意向を尊重する形が取られるようになってきているということです。
また、家族や親しい方々にとって、俗名は故人を思い出すときに親しみやすさを感じるため、戒名を付けずに俗名での彫刻を選ぶ家族も少なくありません。
戒名と俗名のどちらで彫るのが正しいというのはありません。
故人や家族の価値観によるものなので、戒名でも俗名でもどちらで彫っても全く問題ないということです。
大切なのは、故人の意向や家族の思いを尊重し、適切な方法で故人を偲ぶことです。

彫刻を依頼する時の流れ
彫刻をしてもらう時の基本的な流れをお伝えします。
●彫刻に必要な情報を準備する
墓石への彫刻内容は、基本的には以下の4項目となります。
・戒名
・俗名
・亡くなった年齢
・死亡年月日
※キリスト式の場合は、生年月日も彫刻する場合があります。
戒名の文字は、旧字体を使われている場合などもあるため、戒名授与証や白木位牌など、出来るだけお寺につけてもらった文字を確認出来るものを準備しておくと良いでしょう。
●石材店へ依頼の連絡をする
墓石への彫刻は石材店が対応してくれるので、石材店へ連絡をしましょう。
彫刻内容を連絡してから、石材店は現地確認や原稿作成作業などもあるため、彫刻完成までに基本的には2,3週間時間がかかります。
すぐに完成するものではないので、完成時期の希望がある場合は、早めに石材店へ連絡をすることをおすすめします。
石材店への彫刻内容を伝える場合は、電話など口頭のやり取りで聞き間違えなどが無いように、郵便,FAXやメールなど、口頭ではなく文面で伝えることが大切です。
お寺からもらった授与証のコピーや白木位牌の写真は一番正確な情報のため、それを送ったりして知らせることをおすすめします。
彫刻はいつまでに行えば良いのか
彫刻はいつまでに行わなくてはいけないという期限はありません。
一般的には、お墓を既に持っている場合は、納骨までに彫刻を行うことが多いです。
まだお墓をもっていない場合は、建墓を依頼するときに併せて、彫刻も依頼すると良いでしょう。
ですが、彫刻を行うのにいつまでという決まりはないため、必ず納骨や建墓までに間に合わせる必要はありません。
それは、彫刻の文字自体に、故人の魂が宿るわけではないからです。
亡くなった方のご遺族が心身ともに落ち着いてから、改めて彫刻を依頼して行うこともできます。
亡くなられてからすぐにご納骨をする場合や、お寺からのお戒名の授与が納骨までに間に合わない場合もあります。
そういった場合でも、納骨後に彫刻を行うことはできるので、焦らずゆっくり進めることが大切です。
戒名や俗名はどこに彫る場所や文字の色について
◇彫刻する場所について
戒名や俗名は、基本的には彫る場所が決まっており、石塔側面か墓誌に彫ります。
●墓誌
墓誌は戒名やお名前などを彫刻するためのものです。
最近の墓所は、この墓誌という石版を立てることが多くなっています。
墓誌が立っている墓所の場合は、基本的には墓誌に彫刻していきます。
●石塔側面
墓誌が立っていない墓所の場合、和型の石碑の場合は、お石塔側面に彫ります。
昔からある墓所の場合、墓誌がない場合が多いので、側面に彫られていることが多いです。
片方の側面がいっぱいになったら、反対側面に彫っていきます。
●石碑背面、カロート
洋型の墓所の場合は、石碑の背面、もしくはカロート(お骨を納める場所)の蓋石に彫刻することが多いです。
◇彫刻の文字の色について
彫刻の文字の色についても、特別決まりというものはありません。
基本的には素掘り(色を入れない)もしくは、白か黒で色を入れることが多いです。
墓石の色が黒などの場合、素掘りのままでも文字は見えますが、墓石の色がグレーなどの場合、色を入れずに素掘りのままだと、文字が見えづらくなってしまうことがあります。
そのような場合は、色を入れることをおすすめします。
また、墓所によっては文字に朱色が入っている彫刻も目にすることもあるかもしれません。
生前にお戒名をつけてもらって、墓所へ彫刻をする場合、朱色を入れる習わしがありました。
背面に彫られいてるお墓の建立者の文字なども朱色で入れられている場合があります。
その場合、基本的には、亡くなったあとに朱色を抜いて、他のご先祖様と同じかたちにしてもらいます。
彫刻についてよくある質問

-
彫刻する順番は決まっているの?
-
基本的には亡くなった順で彫刻していきます。
ただし、夫婦となり合わせで彫ってもらいたいなどといった希望が事前にある場合は、その分のスペースを空けて彫刻をすることも可能です。
石材店に相談してみると良いでしょう。
-
彫刻の費用の相場はどれくらい?
-
彫刻は文字数に関係なく一人当たりの料金が基本となっています。
相場としては、5万円前後のことが多いでしょう。
ただし地域や寺院によって金額も変わってくるので、依頼する石材店に事前に料金の確認をすることが大切です。
また、生前に戒名や俗名だけ部分的に彫刻してある場合もあります。
そのような場合は、亡くなったあとに、朱色が入っている場合は朱抜や、死亡年月日と亡くなった年齢を追加で彫刻するかたちとなります。
その場合の費用については石材店によって対応が変わってくるので、依頼時に確認すると良いでしょう。
-
依頼する石材店はどこでもいいの?
-
民営霊園の場合、指定石材店制度で霊園に出入りできる石材店が決まっていることが多いです。
そのため基本的には、お墓を建ててくれた石材店に依頼する形となります。公営霊園の場合は、特に決められた石材店などはないため、どの石材店に依頼しても問題ありません。
ただし金額だけで石材店を選ぶのではなく、インターネットでホームページや口コミなどを事前に調べて依頼することが大切です。
石に文字を彫るので、万が一間違えなどがあった場合、修正は困難な作業となります。
信頼できる石材店を選ぶことをおすすめします。
おわりに
墓所での名前や戒名の彫刻は、必ずしもすべての墓所でされているわけではありません。
彫刻を行うかどうかは、費用の問題や、家族・個人の考え方や希望、宗教的な慣習などによって変わってきます。
彫刻をするかどうかや、彫刻を行う時期についても、決まりというものはありません。
家族や親族で話し合ったうえで決めていくとよいでしょう。
また、彫刻は石に文字を彫るため、一度彫ってしまうと修正作業は困難なものとなります。
依頼する石材店は信頼できる業者を選ぶことおすすめします。
平成東武霊園には、一般墓から永代供養墓まで、多彩な区画の様々なタイプのお墓がございます。
それぞれの家族の価値観や供養の形から選択していただくことが出来ます。
大切な方々と共に、ご先祖様と、これから繋いでいく家族のために最善の供養の形を選択していただけばと思います。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
お問い合わせはこちら
- 関連霊園 -