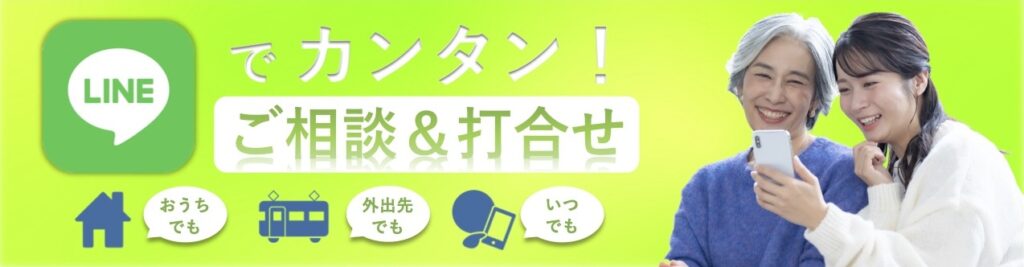無縁墓になるとどうなる?承継者問題、永代供養墓、お墓を守るために安心できる供養のかたちを考える
「無縁墓(むえんぼ、むえんばか)」という言葉を耳にしたことはありますか?
最近はニュースや新聞でも取り上げられることが増え、文字の通り、なんとなく「誰もお参りする人がいなくなったお墓」のことを指すとイメージを持てるかと思います。
お墓参りに行ったときに、自分の近くのお墓の草木がものすごかった、お石塔が見えないくらい草が生えていて、立て札が立っていたというような墓所を見かけたことがある方もいるかもしれません。
少子高齢化や核家族化が進むなかで、「お墓を継ぐ人がいない」「将来、このままでは無縁墓になってしまうかもしれない」と心配される方も少なくないかと思います。
さらに、無縁墓はずっと放置されるのではなく、法律に基づいて整理される可能性があることはご存じでしょうか。
この記事では、無縁墓がなぜ増えているのか、無縁墓になると実際にどうなるのか、そして将来自分のお墓が無縁墓にならないためにできることもあわせて、ご紹介したいと思います。
無縁墓について知ることで、ご自身やご家族のお墓を考えていただければ幸いです。
目次
無縁墓とは?一般的に使われる意味と法律的な定義
「無縁墓(むえんぼ、むえんばか)」という言葉を聞くと、なんとなく「お参りをする人がいないお墓」というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
無縁墓とは、お墓を管理したり供養を続けたりする人がいなくなった状態のお墓のことをいいます。
つまり「お墓はあるけれど、誰もお参りに来ない」「掃除や管理をする人がいない」という状態です。

◇無縁墓の法律的な定義
「無縁墓」は最近ニュースや新聞でよく目にする言葉ではありますが、実は法律上では「無縁墓」という言葉はありません。
ですが、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」という法律によると、「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」を「無縁墳墓等」と定義されています。
そして、承継者のいない無縁墳墓に対して、管理者(霊園やお寺)が一定の決められた手続きや遺族への通知を行った上で、改葬(お骨を移すこと)を進めることができると定められています。
日本では昔から「無縁仏(むえんぼとけ)」という言葉がありました。
家族や縁者がいないために弔われなかった遺骨や、供養する人がいない仏さまを指す言葉で、日本では古くから使われてきました。
現在の「無縁墓」の考え方も、この「無縁仏」という言葉から生まれたのかもしれません。
◇無縁墓になってしまう可能性がある状況とは
「うちには子どもがいるから大丈夫」と思われている方もいるかもしれません。
ですが、実は無縁墓になる可能性はどの家庭にもあるのです。
代表的なケースをいくつか紹介します。
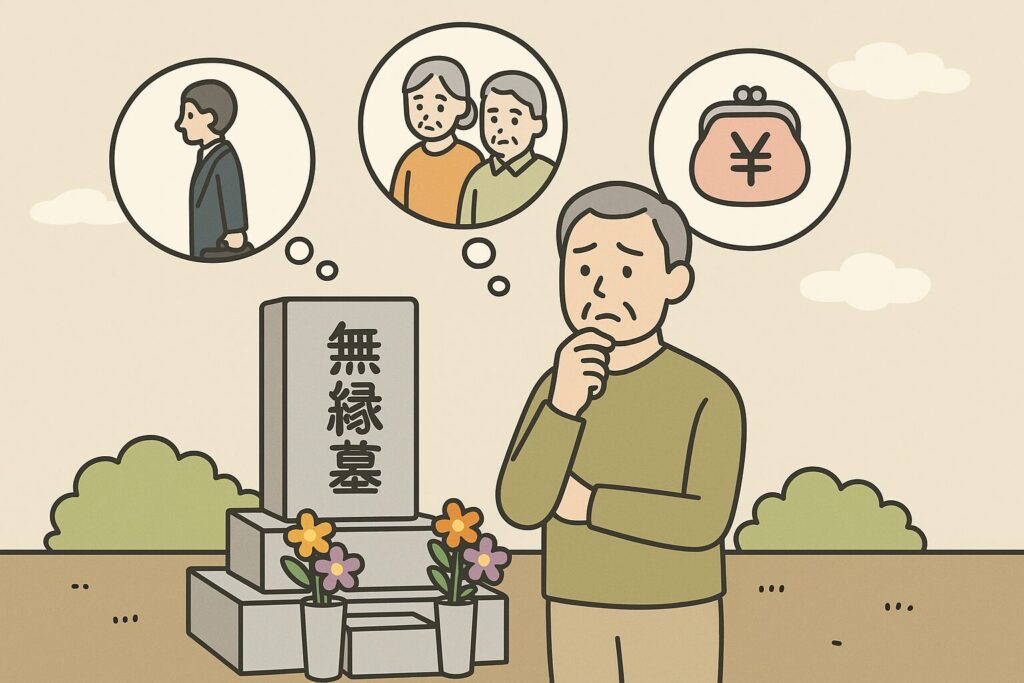
①承継者がいない場合
・子どもがいない、独身で親族がいない
・結婚していても子どもが遠方に住んでいて、お墓を継ぐことができない
・親族はいるが、お墓を引き継ぐ意思がない
②継ぐ人はいても事情があってお墓を守れない場合
・遠方や海外に住んでおり、定期的なお墓参りや掃除に行くことが難しい
・経済的な理由でお墓の維持や管理が出来ない
・高齢や体調の問題でお墓の管理が出来ない
③環境の問題で無縁になってしまう場合
・実家にお墓があるが、お墓参りに行くのに時間や費用がかかる
・公共交通機関の便が悪く、だんだん足が遠のいてしまう
・世代交代とともにお墓への関心が薄れ、気付いた時には放置された状況となっている
このように、数十年後に自分の家のお墓が「無縁墓」となってしまう可能性は、誰にでもあり得るのです。
無縁墓が増えている理由と時代背景
では、なぜ近年、無縁墓が増えているのでしょうか。
その背景には、現代の社会構造の変化やライフスタイルの移り変わりが深く関わっています。
少子高齢化
無縁墓が増える要因としてまずあげられるのが、少子高齢化と家族のかたちの変化 にあります。
日本では少子化が進み、兄弟姉妹がいない一人っ子世帯が多くなっています。
結果として「お墓を継ぐ人がいない」「一人に大きな負担が集中する」という状況が起きやすくなっています。
こうした人口構造の変化は、将来的に無縁墓がさらに増える大きな要因となっています。
未婚率の上昇
令和2年(2020年)国勢調査では、50歳まで一度も結婚していない「生涯未婚率」は、上昇している状況だと判明しました。
結婚しない人が増えることで、そもそも「お墓を承継する子どもがいない」という家庭も増えているのです。
核家族化
核家族化 の進行も無縁墓に大きく関係しています。
昔は、夫婦とその子供という基本的な核家族に加えて、その親族が一緒の家に住むというサザエさんのような拡大家族の方が多かった時代がありました。
ですが、現在は、夫婦と子供だけの核家族のかたちが一般的になっています。
その結果、親や親族のお墓を「自分のこと」として捉えにくい世代が増えています。
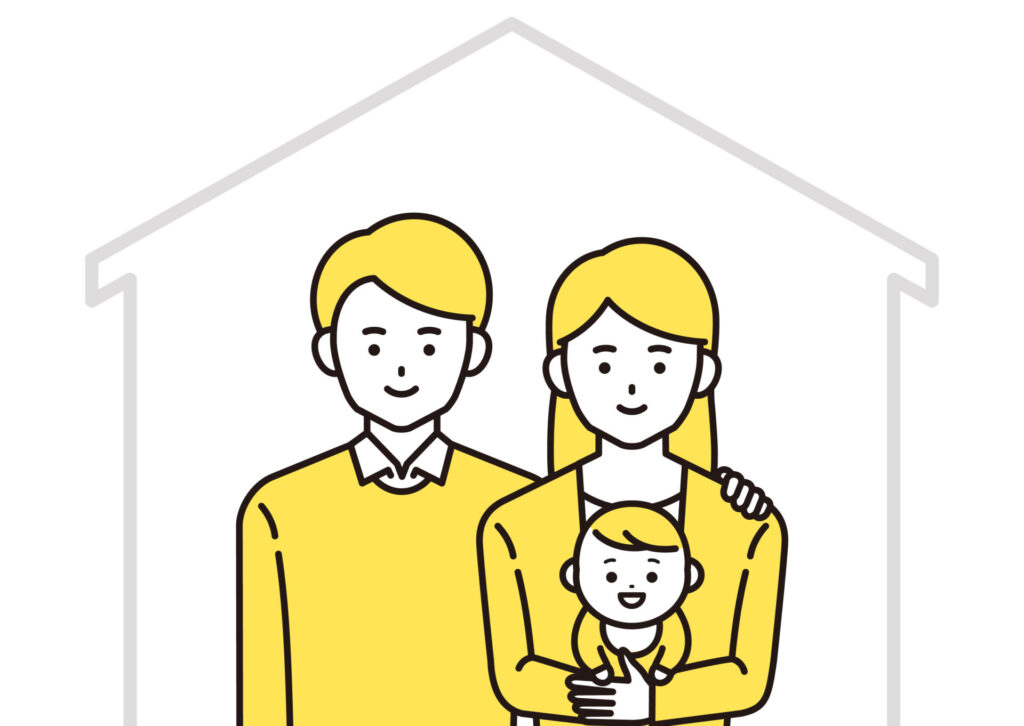
地方と都市部でのライフスタイル
地方では、若い世代が都市部へ移住することで「実家のお墓を継ぐ人がいない」という状況が生まれやすくなっています。
一方で、都心に住む人は、「仕事や生活が忙しくなかなかお墓に行くことができない」「お墓参りに行くのに時間や費用がかかる」といった理由で、お墓に行く機会が減少する状況となっています。
地方と都市部で状況は異なりますが、結果的に無縁状態になってしまう要因となっています。
費用負担や承継者不足
お墓を管理・維持していくためには、定期的なお参りや掃除だけではなく、墓石の補修や、霊園へ年間管理料の支払いなども必要になります。
こうした費用や手間を「大きな負担」と感じる家族も少なくありません。
こういった費用や手間を将来にわたって維持していくのは難しいと判断し、あえて墓じまいを選ばれる方も増えています。
また、昔はお墓は兄弟や親族が力を合わせて守っていたものですが、今では一人では背負いきれないといった変化も要因となっています。
無縁墓の増加は、個人や家庭の事情だけでは片付けられない部分も多くあります。
多くの自治体や霊園は「無縁墓をどのように整理していくか」「時代に合った新しい供養の形をどう広げていくか」という大きなテーマに直面しています。
同時に、この無縁墓の増加は現代の価値観の変化を反映しているともいえます。
昔は「お墓を守っていくもの」という考え方が当たり前でしたが、今では「無理に継がなくてもいい」「永代供養や合祀墓といった選択肢がある」と考える人が増えてきました。
無縁墓の増加は、ネガティブな問題ではあるものの、「供養の多様化」が進んでいることを象徴しているのかもしれません。
無縁墓になるとお墓は整理される?
無縁墓になってしまったら、そのお墓はどうなるのか、不安に思われる方も多いかと思います。
ここでは、霊園や自治体がどのような手順で無縁墓の整理や改葬を行うのかご説明します。
◇霊園やお寺の権限とルール
霊園やお寺は「無縁墓だから」といって自由に撤去や改葬ができるわけではありません。
「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」があり、無縁墓に関することは、この法律に基づいて行われます。
霊園やお寺は、お墓の管理者として一定の権限を持ってはいますが、それはあくまで法律に沿った範囲に限られています。
つまり、しっかりと法律に基づいた手続きをしなければ、勝手に無縁墓を整理することは出来ない仕組みとなっています。
◇公告の必要性
無縁墓と判断された場合、霊園やお寺はまず「公告(こうこく)」という手続きを行わなくてはいけません。
これは「このお墓を管理する方はいませんか?」という呼びかけを、霊園内や市町村の掲示板になどに掲示することです。
公告期間は法律で定められており、少なくとも1年以上公告をするのが一般的です。
その公告を行っている期間にお墓の承継者だという人が現れたら、お墓は無縁墓として処理されずに済みます。
期間内に連絡してくる人が誰もいなければ、正式に「無縁墓」と認定され、次の段階へ進みます。
◇遺族への確認
公告のほかに、霊園やお寺は可能な限り遺族へ連絡を取れるよう対処します。
それでも反応がなく、承継者がいないと判断されてしまった場合、管理者はお墓を整理することができます。
多くの場合、お墓の遺骨は霊園やお寺が管理する 合祀墓(合葬墓) に改葬され、きちんと供養が続けられるようにします。
無縁墓だからと言って雑に扱われるというわけではなく、あくまでも法律と宗教的配慮の両方を踏まえた上で対応してくれる場合が多いです。
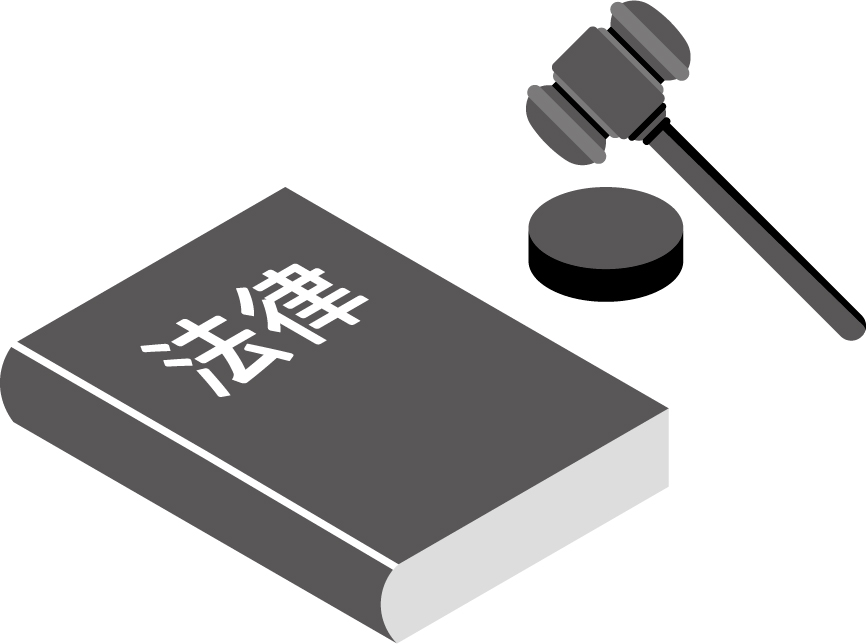
もしも公告や通知をせずに、管理者が無縁墓と判断をしたうえで勝手に整理や撤去してしまうと、後から遺族が現れた際に大きなトラブルにつながります。
そのため、管理者の方も、法律に基づいた手続きをしなくてはいけないのです。
公告の期間や方法、改葬の手順が細かく定められているのも、こうしたトラブルを未然に防ぐためです。
無縁墓にならないために 大切なご先祖様の眠るお墓を守るためにできること
無縁墓は特別な家庭に起こる問題ではなく、誰にでも起こり得る身近な課題だと認識してもらえましたでしょうか。
子どもや孫が遠くに住んでいる、将来お墓を継ぐ人がいない、管理費や維持の負担が大きい――こうした状況は決して珍しくありません。
どこの家庭でも聞こえてくる身近な内容です。
だからこそ、「将来、無縁墓にならないためにどうしたらよいのか」を考えることが大切です。
◇永代供養墓という選択
これからお墓を購入することを考えている方は、霊園やお寺が責任を持って供養を続けてくれる 永代供養墓 を選ぶ方法があります。
永代供養墓は、承継者がいなくても、霊園やお寺が永代にわたって供養、管理・維持してくれるため、例え承継者がいなくなってしまったとしても、お墓のことを心配する必要はありません。
また、ご夫婦やご家族単位で利用できる 家族墓 も人気です。
お墓に入れる人数があらかじめ決まっているため、世代を重ねて継承する必要がなく、後の世代に負担を残さずに済みます。
◇墓じまいという選択肢
すでにお墓を持っている方で「将来お墓を継いでくれる人がいない」と分かっている場合には、墓じまい も一つの手段です。
お墓を整理し、遺骨を合祀墓や永代供養墓へ移すことで、無縁墓になる前にしっかりと供養の形を整えることができます。

◇終活の一環として、家族とお墓について相談しておく
終活の一環として 生前からお墓について考えておく 方も増えています。
「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、早めに霊園や石材店に相談したり、お墓の契約内容を確認したりしておくことも重要です。
そして、家族や親族とも将来のお墓の選択肢を確認しておけば、家族に余計な心配をかけずに済み、自分自身の心配事も1つ少なくする事できます。
事前に話しておくことで、家族への負担も軽くすることになります。

新しい供養のかたちと平成東武霊園として出来ること
現代では、お墓を継ぐ人がいなくても安心して供養できるかたちが多様化してきて、さまざまな選択肢があります。
代表的なのが 永代供養墓 です。
承継者がいなくても安心してお墓を任せることが出来ます。
また、樹木や花など自然のもとに眠る樹木葬 や、複数の方と一緒に眠る合葬墓や合祀墓も注目を集めています。
これらはどれも承継者が不要で、家族に負担をかけずに安心できる供養のかたちとして、最近ではとても人気のあるお墓のスタイルです。
無縁墓を防ぐためには、霊園側のサポートも欠かせません。
平成東武霊園では、将来お墓が無縁にならず、安心してお墓をご購入いただけるようにさまざまな選択肢があります。
平成東武霊園には、さまざまな永代供養墓があります。
夫婦墓や家族墓、近年人気の高まっている樹木葬、合葬墓、皆さまのご希望を伺ったうえで一番合うお墓を選択していただくことができます。
また、「将来安心プラン」という承継者の不安をしなくてよいプランもあります。
これは一定期間は個別のお墓を持ち、将来は霊園が責任を持ってお墓じまいをして合葬墓へ改葬してくれる仕組みになっているので、将来のお墓に対する不安を軽減することができるかと思います。
永代供養墓や家族墓のご案内はもちろん、お客様それぞれのご事情に合わせた最適な方法をご提案できたらと思います。
平成東武霊園についてもっと詳しく
おわりに
無縁墓は、他人事ではなく、近年では誰にでも起こり得る身近な問題です。
お墓を守ってくれる人がいなくなった時、霊園やお寺が一定の手続きを経たうえで、整理や合祀を行うこともありますが、一番大切なのは「無縁墓にならないように、事前に備えること」です。
事前に備える方法としてあげられることは、永代供養墓や家族墓といった承継者に負担をかけないお墓を選ぶことや、生前から終活の一環として、周りの家族や親族に相談しておくことです。
平成東武霊園では、永代供養墓にもいくつか種類があるため、ご家族様それぞれの状況や希望に沿ったお墓のかたちを選択してもらうことが出来ます。
また、将来の承継を心配しないで済むプランもご用意しております。
こうした新しい供養のかたちは、「無縁墓を減らすための取り組み」ともいえるでしょう。
無縁墓を他人事とせず、ご自身やご家族の供養のあり方を今一度考えるきっかけにしていただければと思います。
監修者情報

渡辺裕
(わたなべゆたか)
1984年生まれ。千葉県松戸市育ち。実家が石材店のため、幼い頃からさまざまなご家族様の供養に触れて育つ。大学卒業後は法人向けソリューション営業に従事し、その後当石材店に勤務。多くのご家族様のお墓の建立に携わり、2017年に4代目店主として代表取締役に就任。終活に関する資格を多数所有し、幅広い知識と経験でお客様に寄り添ったサポートを心がけている。
有限会社 千代田家石材店/代表取締役
一般社団法人 日本石材協会/認定 お墓ディレクター 2級 認定番号 21-200080-00
一般社団法人 終活カウンセラー協会/終活カウンセラー 2級
一般社団法人 日本看取り士会/看取り士
一般社団法人 日本尊骨士協会/尊骨士
お問い合わせはこちら
- 関連霊園 -